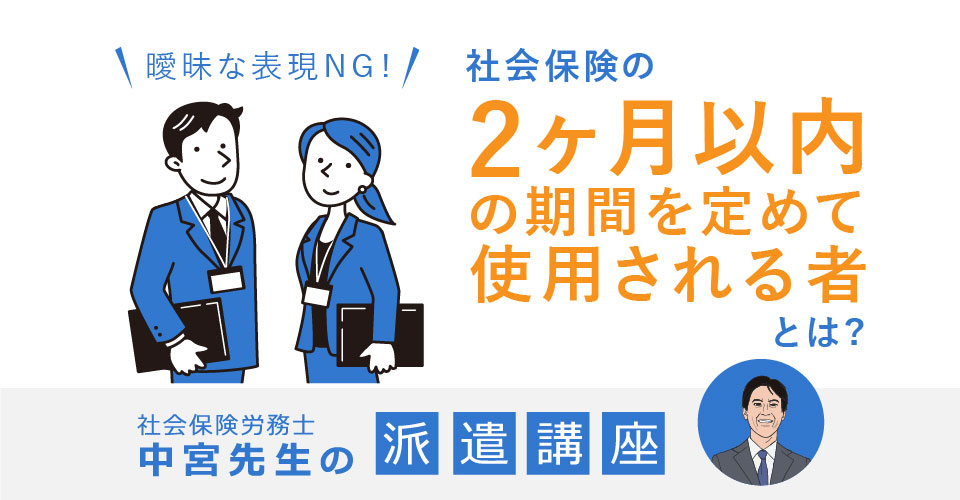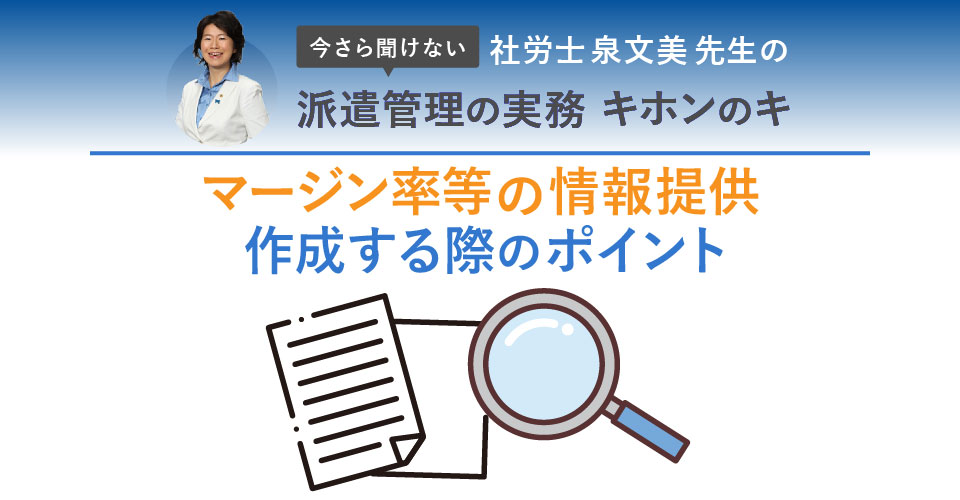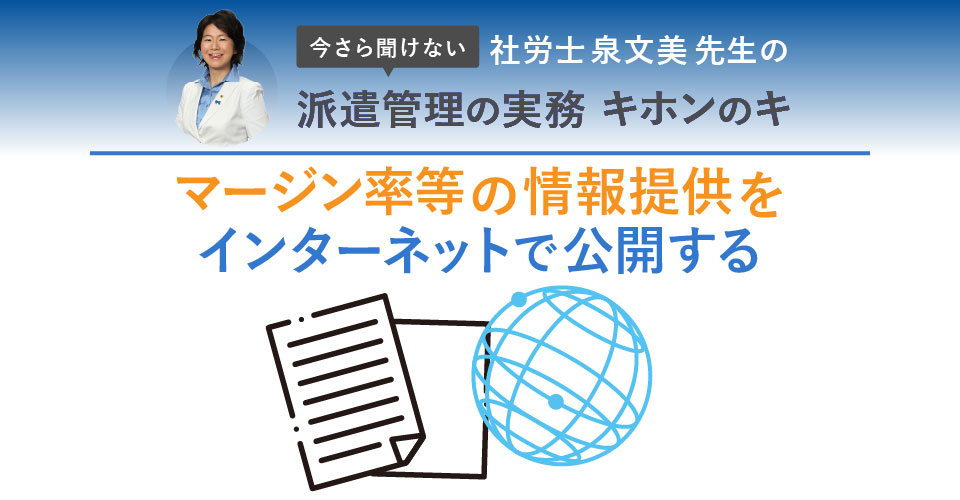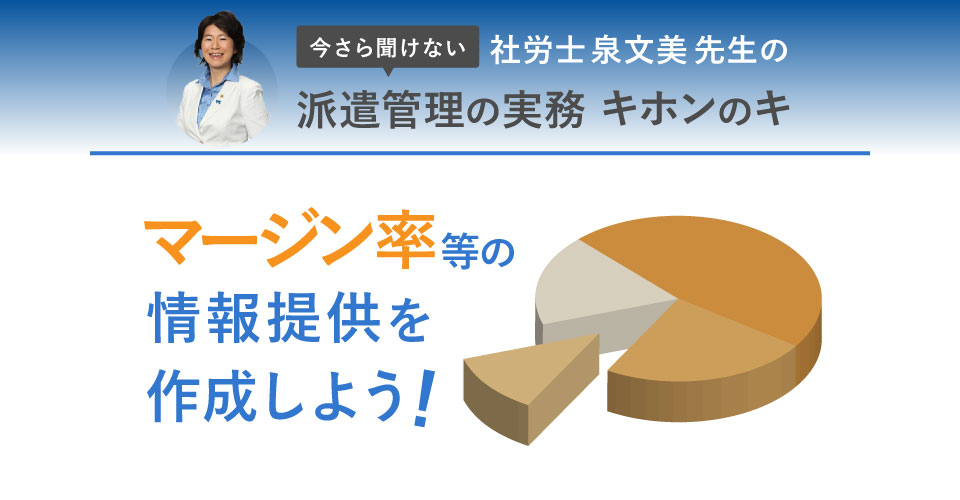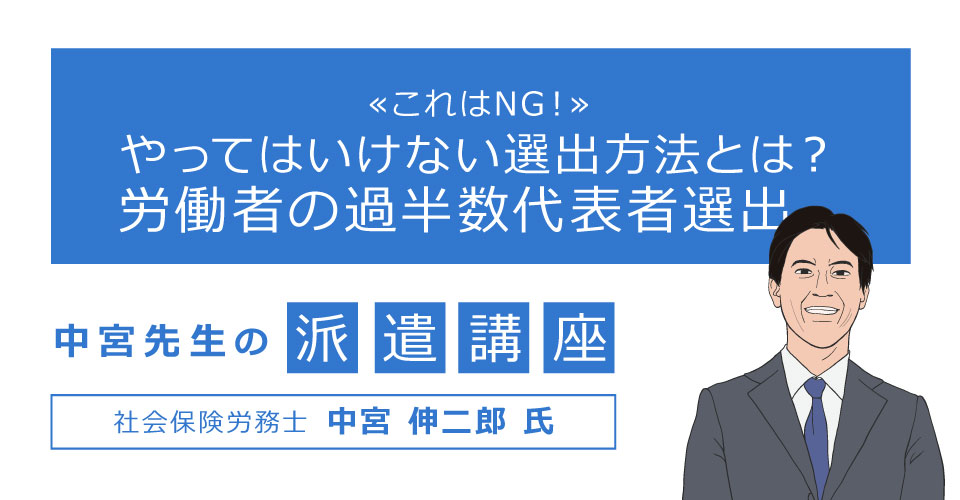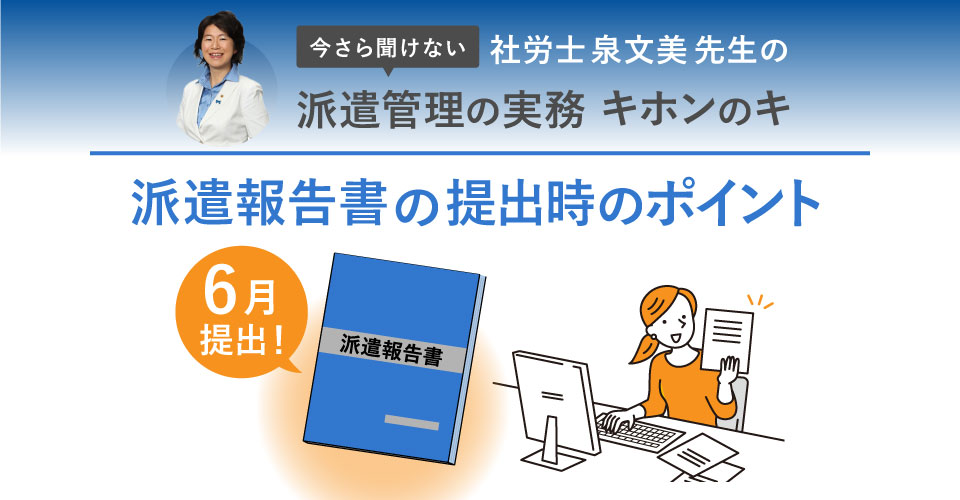

派遣報告書をプリントアウトしただけで、慌てて送っていませんか?
この記事を読めば、「忘れ物無し!」「労働局の追加督促無し!」
スムーズに提出できます!
派遣会社の皆さま、初めまして。
今回より、新しくコラム記事執筆を担当することになりました、
社会保険労務士、みなとみらい人事コンサルティング代表の泉文美(いずみ あやみ)と申します。
以後、よろしくお願いいたします。
※この記事は 2025年5月20日時点の情報を元に解説しています。
目次
社会保険労務士 みなとみらい人事コンサルティング代表 泉文美

初回ですので、このコラム記事執筆を任された私がどういった人物なのか、簡単に自己紹介をさせていただきます。
私は2012年に社会保険労務士として開業し、顧問先の人事労務関係のサポートをしております。
また、派遣会社は受講することが義務づけられている派遣元責任者講習の講師をずっと務めております。
◆株式会社フィールドプランニング派遣元責任者講習 講師紹介
現在は新宿会場での登壇と、オンラインでのビデオ出演をしております。
延べ13年、前は新宿会場以外にもオフライン会場がございましたので、関東全県、及び富山県にも出向き、派遣法の解説をしてきました。
通算講義回数は300回を、延べ受講者数は6,000人を超えております。
また、派遣元責任者講習に加え、派遣先責任者講習、職業紹介責任者講習の講師も務めております。
おかげさまで、派遣・紹介関係の顧問先が増えまして、今では当事務所の顧問先の95%が、派遣・紹介関係会社となっております。
派遣に関する申請から報告書、調査対応も全国にまたがり、顧問先の業務を⽇々サポートしております。
そういった経緯から、「法務と実務の両面に精通し、現在進行形で全国対応している、派遣に詳しい社労士」として、今回コラム執筆のご依頼をいただくことになりました。
一般的な説明だけでなく、私が日々実務を行う中でのリアルな体験談も盛り込んで、ここでしか読めない、「明日から使えるお役立ち記事」を目指していきますので、よろしくお願いします!
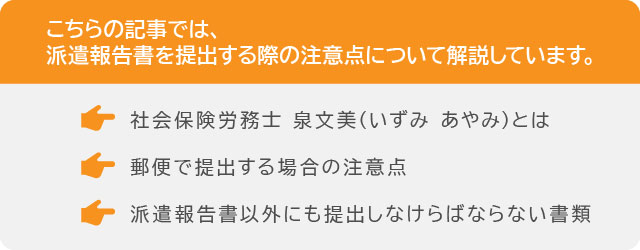
今回のテーマは、時期的に旬な派遣報告書について解説します。
報告書の書き方・数値の集計方法など、丁寧にすべてを解説するにはボリュームが大きくなりすぎる為、
来年の4~5月のコラム記事で、お話していきたいと思います。
派遣報告書を提出する際のポイント
今回は、報告書を労働局に提出する際のポイントを説明いたします。
皆様の会社宛てに、労働局からこのような案内が届いていると思います。
これは東京労働局のもので、各労働局によって案内は異なります。
自分の会社に送られてきた案内を実際に手元に置きながら、以下の点を見比べると、より分かりやすくていいですよ~!
ポイントその1 提出方法
来庁しての提出も可ですが、事務作業効率の観点から、ほとんどの労働局は郵便提出を求めています。
労働局によっては、簡易書留を指定されていたり、担当者名が指示されたりしていることもあります。必ず確認して、指示通りの宛先・郵便方法で提出するようにしましょう。
電子申請ももちろん可能ですが、e-Gov取得が必要です。
私のような社労士に代行を依頼する場合は、e-Govアカウントを社労士に教えて入力させる、ということは現実的ではないので、郵送提出が多くなると思います。
郵送の場合、提出するのは派遣報告書3部(正・副・控)です。
「控」は労働局の受付印を押されて、会社に返送されます。返信用封筒を忘れずに用意しましょう。
返信用封筒も簡易書留などを指定されることもあります。必要な金額分の切手を貼るようにしましょう。
返信用封筒に切手を貼り忘れると、切手を送るよう労働局から督促が来ることがあります。
ポイントその2 報告書につける書類
派遣報告書だけでなく、添付書類も忘れずに送信用封筒に入れます。
それぞれ、正・副添付用に2部、白黒コピーでとって付けましょう。
控は会社に戻ってくる分ですから、添付書類は要りません。
派遣に限ったことではないのですが、コピーは白黒が好まれます。
例えば、派遣の労使協定などですと、会社と労働者代表の印鑑がそれぞれ押してあることが多いと思います。
労使協定原本は会社で保管すべきもののため、
必ずコピーを提出しますが、最近のカラーコピーはとても鮮明に複製できてしまうため、
「原本を送られてしまったのか」と労働局の担当者を無駄に悩ませることになり、余計な問い合わせが皆様に来てしまうことになります。
添付書類にあたるもの
では、具体的な添付書類について。
⼤多数の、労使協定⽅式を採⽤している派遣会社では、同一労働同一賃金の労使協定すべてのページのコピーを用意する必要があります。

この労使協定自体の解説は、今後のコラムで行いますので、楽しみにしていてくださいね
労使協定原本は会社で保管すべきものですので、上記の通り、必ず白黒コピーをとってつけてください。
労使協定条文部分だけでなく、賃金の等級表などが別紙になっていたら、それも含めて労使協定ですので、忘れずに全部コピーするようにしましょう。
労使協定以外にもコピーが必要な箇所が何箇所かあります。
特定の文言が記載されている場合、該当箇所に関連するページのコピーも必要です。
例えば、労使協定の中に「就業規則第〇条に基づき~」という記載がある場合、該当する就業規則のページのコピーも、添付しなければなりません。
「別紙評価シートに基づき~、公正に能力を評価する」という記載の場合も、やはり評価シートのコピーが必要になります。
労働局によって独⾃の書類の提出を求められることも
また、このように、
労働局によっては、独自のチェックリストなどが案内一式に含まれていることがあり、手書きでの作成が求められることがあります。
だだし、チェックリストなどが入っていたとしても、あくまで自社内の確認用であることもあります。
提出が必要かどうかは届いた案内を確認しましょう。
電子申請の場合はコピー(正・副・控)や返信用封筒はもちろん不要ですが、このような添付書類を忘れることがあるので、特に注意しましょう。
特に電子申請ですと、「昨年と同じように申請すればいいから」と思ってしまいがちです。労働局から郵便で届く案内を読まないで、パンフレットだと思って捨ててしまう、ということがありがちなので、注意してくださいね。
さいごに
当事務所では派遣報告書の提出に関する相談もいつでも受け付けています。
何かありましたら、まずは下記、当事務所HPのお問い合わせフォームから質問してくださいね。初回相談は無料です。

解説者
みなとみらい人事コンサルティング 代表
泉 文美(いずみ あやみ)
横浜生まれ。2005年東京大学卒業。
ハローワーク、労働基準監督署、労働局、厚生労働省勤務経験有。
2012年社会保険労務士事務所開業。
開業当初より厚生労働省指定「派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習」講師を務める。派遣・紹介関係の顧問先多数。講演・著述の依頼もこなす。
法務と実務両面に強い、派遣・紹介特化型社労士として、役所での勤務経験も活かし、「役所対応に強い社労士」として定評がある。
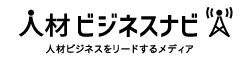
 派遣社員と労災保険
派遣社員と労災保険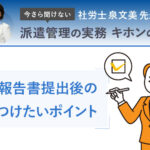 派遣報告書提出後の気をつけたいポイント
派遣報告書提出後の気をつけたいポイント